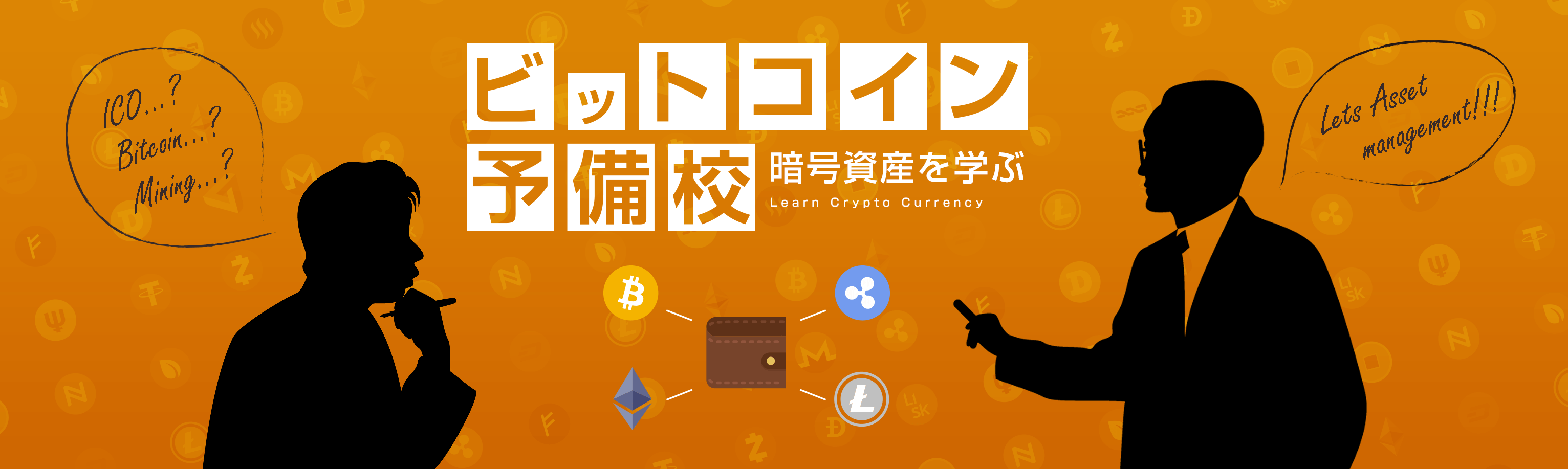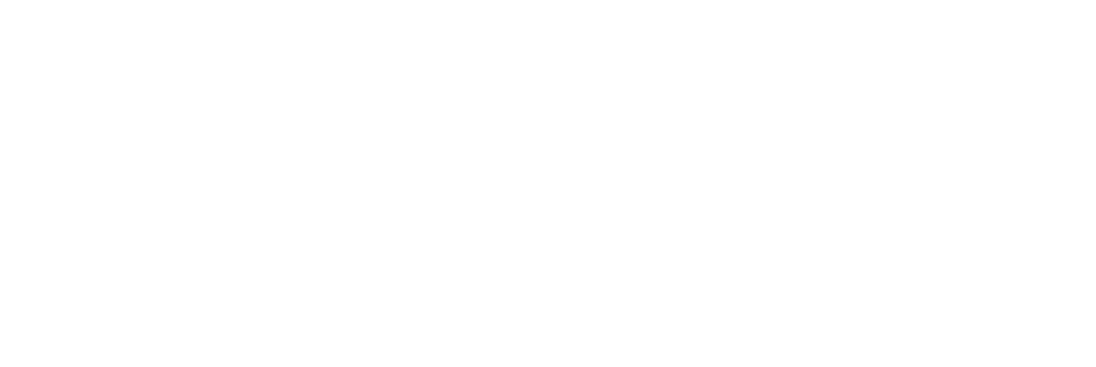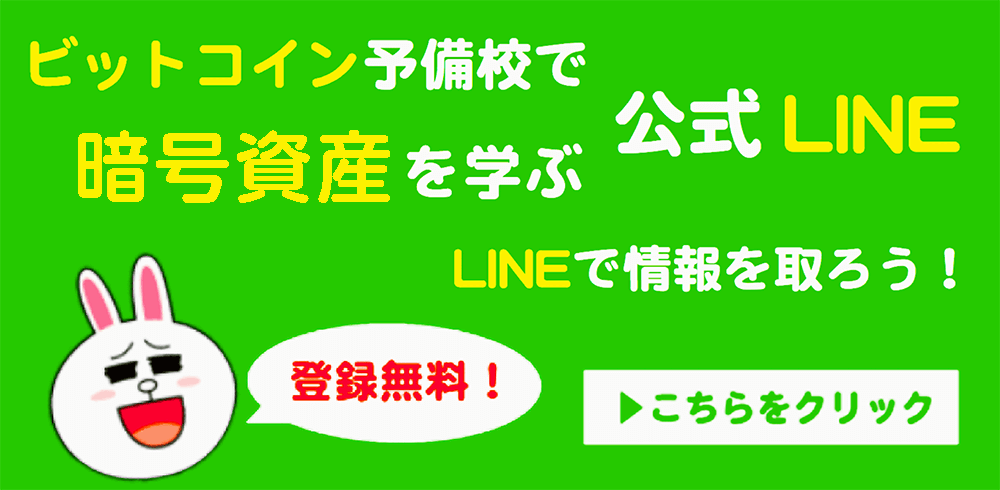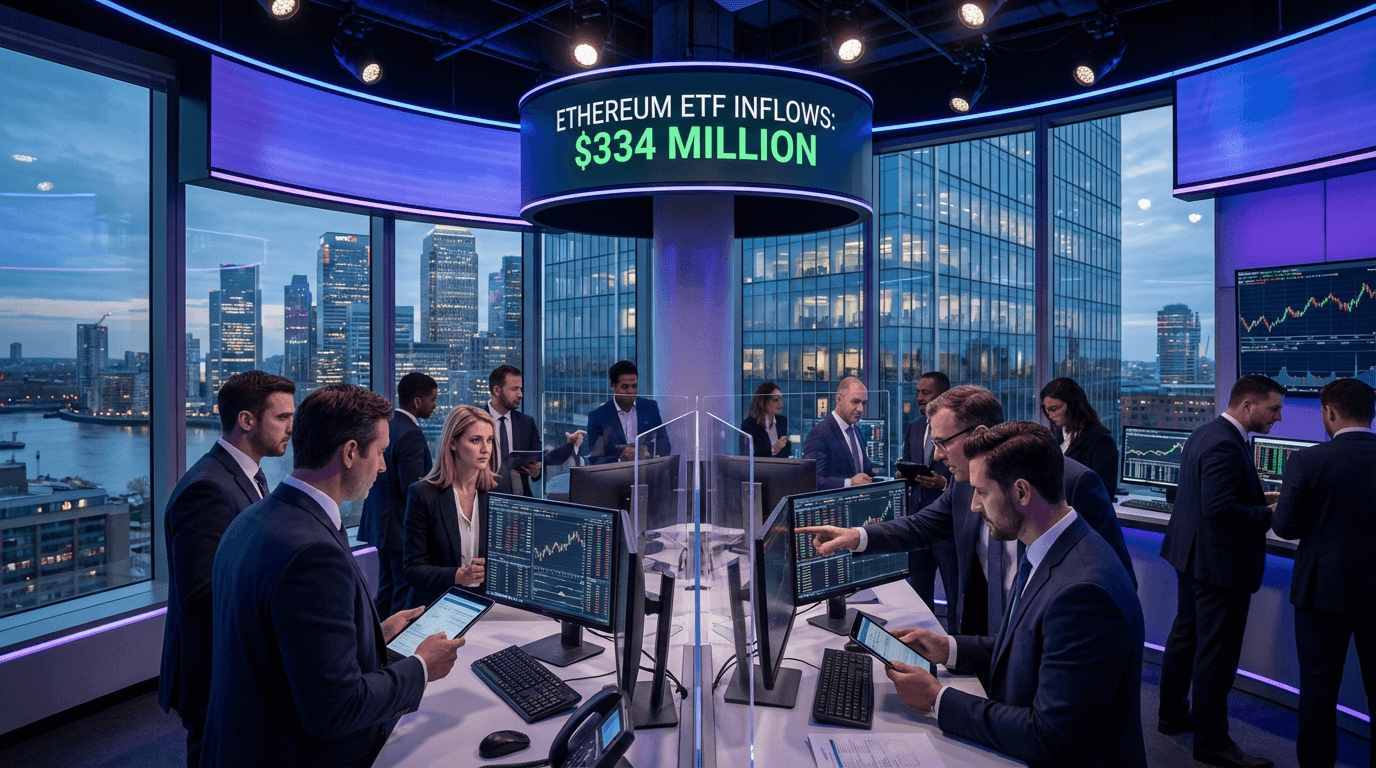目次
【ビットコイン予備校】2025年11月第1週|注目ニュースまとめ
ビットコインは弱気相場入りし、市場は恐怖に包まれた。しかし──その裏で、機関投資家は静かに買い増しを続けていた。
📅 2025年11月3日〜11月9日の注目ニュース
- ✅ ビットコインが弱気相場入り – 最高値から20%超下落、10万ドル割れ
- ✅ JPモルガンが17万ドル予測 – 金との比較で理論上の適正価格を算出
- ✅ 日本3メガバンクのステーブルコイン共同発行 – 金融庁が全面支援
- ✅ JPモルガンのBTC ETF保有64%増 – 第3四半期に207万株追加購入
- ✅ ジーキャッシュ(ZEC)が1ヶ月で4倍 – プライバシー銘柄に資金流入
- ⚠️ USDXデペッグ事件 – 合成型ステーブルコインが0.6ドルまで下落
- ⚠️ カザフスタンが10億ドルの暗号資産準備基金 – 2026年初頭設立予定
今週の買い度数
短期目線(数週間): 5/10点
ビットコインは10万ドルの重要サポートラインで攻防中。短期筋の97%が含み損状態で下落余地は限定的だが、マクロ経済の不透明感が重し。
中期目線(数ヶ月): 7/10点
JPモルガンが17万ドル予測を発表し、実際に保有を64%増加。レバレッジ解消完了で市場構造は健全化。中期的には買い場。
長期目線(1年以上): 9/10点
ビットコインと金のボラティリティ比率が2.0を下回り、機関投資家にとって「許容可能なリスク」水準に到達。国家レベルでの採用も進展し、5〜10年スパンでは「歴史的な買い場」の可能性。
📰 注目ニュース①: ビットコイン弱気相場入り──しかし機関投資家は逆行
11月4日、ビットコインは最高値から20%以上下落し、正式に「弱気相場入り」した。
10万ドルの心理的節目を割り込み、一時は9万5,000ドルまで下落。市場は恐怖指数が「極度の恐怖」領域まで落ち込み、SNSには悲観的な声が溢れた。
しかし──。
その裏で、JPモルガンは第3四半期にブラックロックのビットコインETFを207万株追加購入していたことが判明した。これにより、JPモルガンの保有総数は528万株となり、6月から64%増加している。
・第3四半期の追加購入: 207万株
・保有総数: 528万株
・6月からの増加率: 64%
・ビットコイン価格予測: 17万ドル
「17万ドルまで上がる」と予測したJPモルガンは、自ら買い増しを実行していた。これは単なる「口先だけの予測」ではなく、実際の資金を投じた「確信」の表れだ。
大衆が売る時、賢者は買う
投資の格言に「人の行く裏に道あり花の山」というものがある。
今回の状況はまさにその典型だ。大衆が恐怖で売る中、機関投資家は冷静に買い増しを続けている。
なぜそんなことができるのか? 答えは単純だ──彼らは「価格」ではなく「価値」を見ているから。
大衆は「価格」を見る。機関投資家は「価値」を見る。
この違いが、すべてを決定づける。
JPモルガンの分析では、ビットコインの現在価格は金と比較したボラティリティ調整後の適正価値より約6.8万ドル低いという。
つまり──市場はまだ、ビットコインの真の価値を完全には織り込んでいない。大衆が「暴落だ」と騒ぐ中で、機関投資家は冷静に「割安だ」と判断しているのだ。
JPモルガンの17万ドル予測の詳しい分析と、金との比較から見えた「真の価値」については、以下の記事で深掘りしています。

📰 注目ニュース②: 日本3メガバンクのステーブルコイン共同発行──制度化が加速
11月7日、金融庁は歴史的な発表を行った。
三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行の3メガバンクによる共同ステーブルコイン発行の実証実験を、新設した「決済高度化プロジェクト(PIP)」で支援すると発表したのだ。
片山さつき金融相も「金融庁がサポートする」と明言し、国を挙げた推進姿勢を示した。
100万円の壁が消える
この実証実験で最も重要なのは、100万円の送金上限が撤廃されるという点だ。
既存の電子決済手段には100万円の上限があるが、今回の信託型ステーブルコインではこの制約が適用されない。これが意味するのは、企業間の大口決済、国際貿易、グローバル送金など、本格的な商用利用が可能になるということだ。
・参加銀行: 三菱UFJ、みずほ、三井住友
・支援機関: 金融庁(決済高度化プロジェクト)
・送金上限: 100万円制限なし
・対応通貨: 円建て + 米ドル建て(予定)
・タイプ: 信託型(100%法定通貨担保)
さらに、円建てだけでなく米ドル建ても視野に入れており、日本のステーブルコインが国際決済の基盤となる可能性を示唆している。
なぜ弱気相場の今、日本政府は動いたのか?
ここで重要な問いが浮かぶ。なぜビットコインが弱気相場に入った今このタイミングで、日本政府は大きく動いたのか?
答えは──市場が冷静な時こそ、制度を整える絶好のタイミングだからだ。
バブル期に制度を作ろうとすると、投機熱に引きずられて歪んだ規制ができてしまう。しかし、市場が落ち着いている今なら、冷静に長期的な視点で制度設計ができる。日本政府は、暗号資産市場の本質を理解している。
3メガバンクのステーブルコイン戦略の詳細と、100万円上限撤廃が切り拓く「規格統一」の未来については、以下の記事で詳しく解説しています。

📰 注目ニュース③: USDXデペッグ事件──ステーブルコインの脆弱性が露呈
一方で、今週は暗号資産市場の「リスク」も浮き彫りになった。
合成型ステーブルコイン「USDX」が大幅なデペッグ(価格乖離)を起こし、0.6ドルまで下落したのだ。これは、Balancerプロトコルへの攻撃が引き金となり、USDXの担保不足が明らかになったことが原因だ。
ステーブルコインは「安定」ではない
この事件が教えてくれるのは──すべてのステーブルコインが安定しているわけではないということだ。
特に「合成型」や「アルゴリズム型」のステーブルコインは、担保の健全性やメカニズムの設計に依存しており、ストレステストに弱い。
合成型・アルゴリズム型:
担保不足や設計欠陥でデペッグリスク大(USDX事件が典型例)
信託型(法定通貨100%担保):
デペッグリスク小、規制準拠で安全性高い(日本3メガバンクが採用)
日本の3メガバンクが採用した「信託型」という選択は、こうしたリスクを回避するための賢明な判断だったと言える。
📰 その他の注目トピック
🔒 プライバシー銘柄の復権──ジーキャッシュが1ヶ月で4倍
プライバシー重視の仮想通貨Zcash(ZEC)が過去1ヶ月で約4倍上昇し、時価総額100億ドルを突破した。アーサー・ヘイズ氏などの著名投資家の支持や、グレースケール関連商品の人気拡大が上昇を後押ししている。
ビットコインが下落する中、資金が特定の「テーマ銘柄」に流れる動きが見られる。
🇰🇿 カザフスタンが10億ドルの暗号資産準備基金
カザフスタンが最大10億ドル規模の国家仮想通貨準備基金を2026年初頭までに設立すると発表。押収資産と国営マイニング収益を原資として、ETFや関連企業に投資する方針だ。
国家レベルでの暗号資産採用が、新興国を中心に加速している。
💡 ビットコイン予備校の結論: 今はクリプトは買いなのか?
今週の動きを総合すると、ビットコイン予備校としての結論は明確だ。
短期的にはリスクがあるが、中長期的には明確な買い場である。
①機関投資家の行動が雄弁
JPモルガンが「17万ドル」と予測し、実際に64%も買い増しを実行。確信に基づく行動だ。
②市場構造の健全化
レバレッジ解消が完了し、過剰な投機が排除された。現在の価格下落は「バブル崩壊」ではなく「正常化」のプロセス。
③制度的成熟の加速
日本の3メガバンクによるステーブルコイン実証、カザフスタンの国家準備基金など、制度レベルでの進展が顕著。
④ボラティリティの改善
ビットコインと金のボラティリティ比率が2.0を下回り、機関投資家にとって「許容可能なリスク」水準に到達。
【ただし注意すべき点】
⚠️ 短期的な変動リスク: マクロ経済の不透明感が続く中、短期的にはさらなる下落の可能性もある。一括投資ではなく、分散投資・時間分散を推奨する。
⚠️ ステーブルコインのリスク: USDX事件が示したように、すべてのステーブルコインが安全ではない。信託型など、信頼性の高いものを選ぶべきだ。
【投資家へのアドバイス】
今、市場は恐怖に包まれている。しかし──恐怖こそが、最高の機会だ。
大衆が「終わった」と言う時、賢者は「始まった」と知っている。JPモルガンのように、データと論理に基づいて判断し、長期視点を持つこと。そして、感情ではなく理性で行動すること。
それこそが、この弱気相場から学ぶべき最も重要な教訓だ。
なぜ弱気相場こそチャンスなのか?機関投資家の動きから学ぶ「逆張り」の本質については、以下の記事で詳しく解説しています。

「相場の終わりは、いつも静かに始まる」──その真意を、今こそ噛み締めるべき時だ。