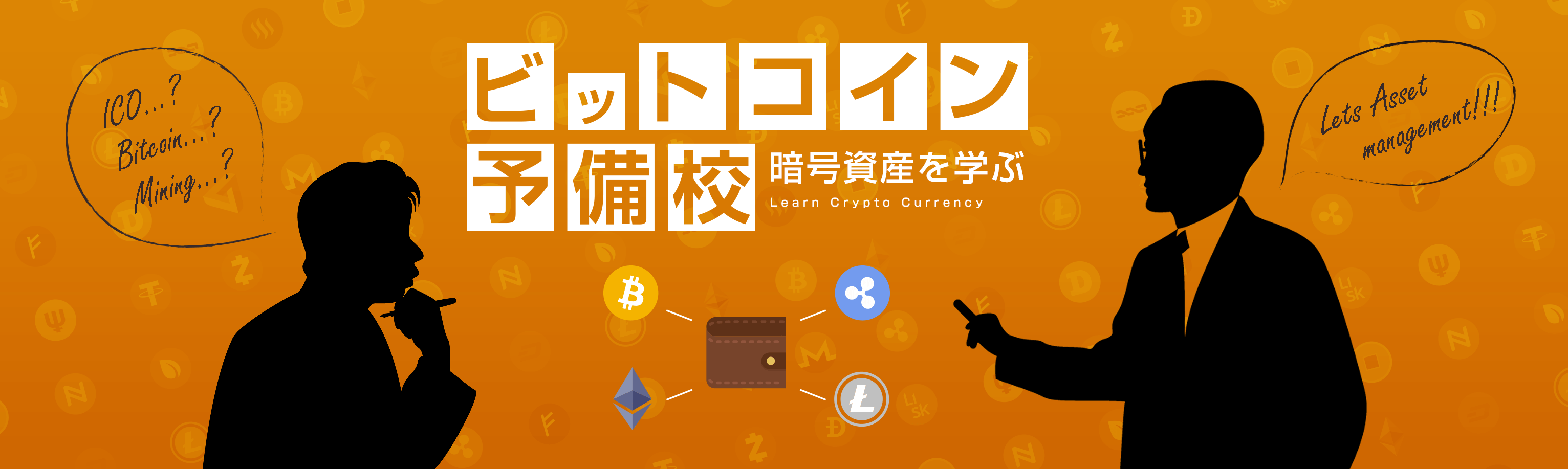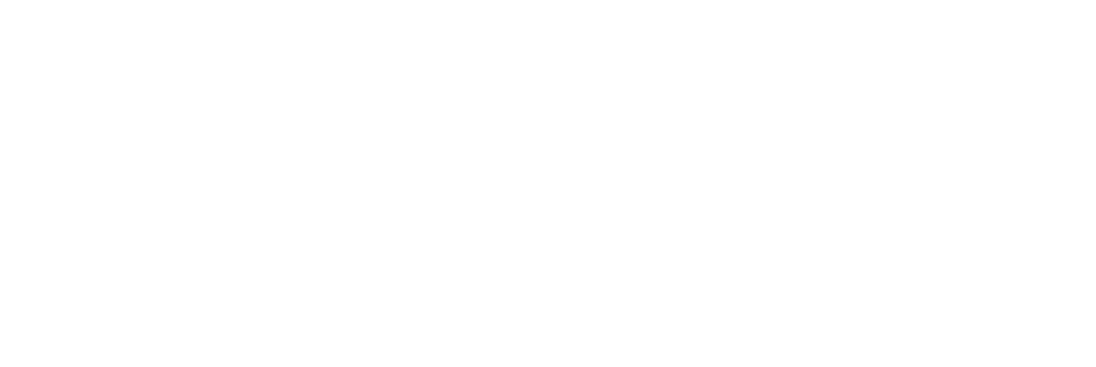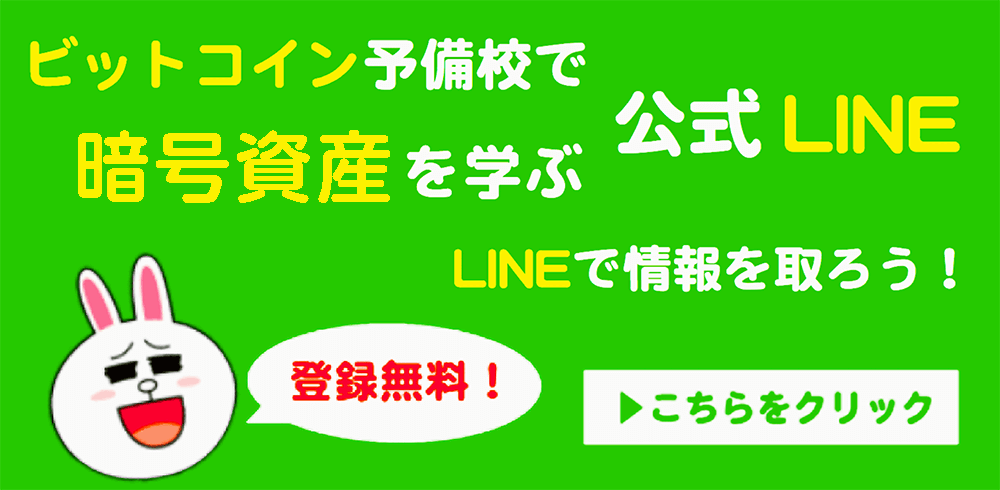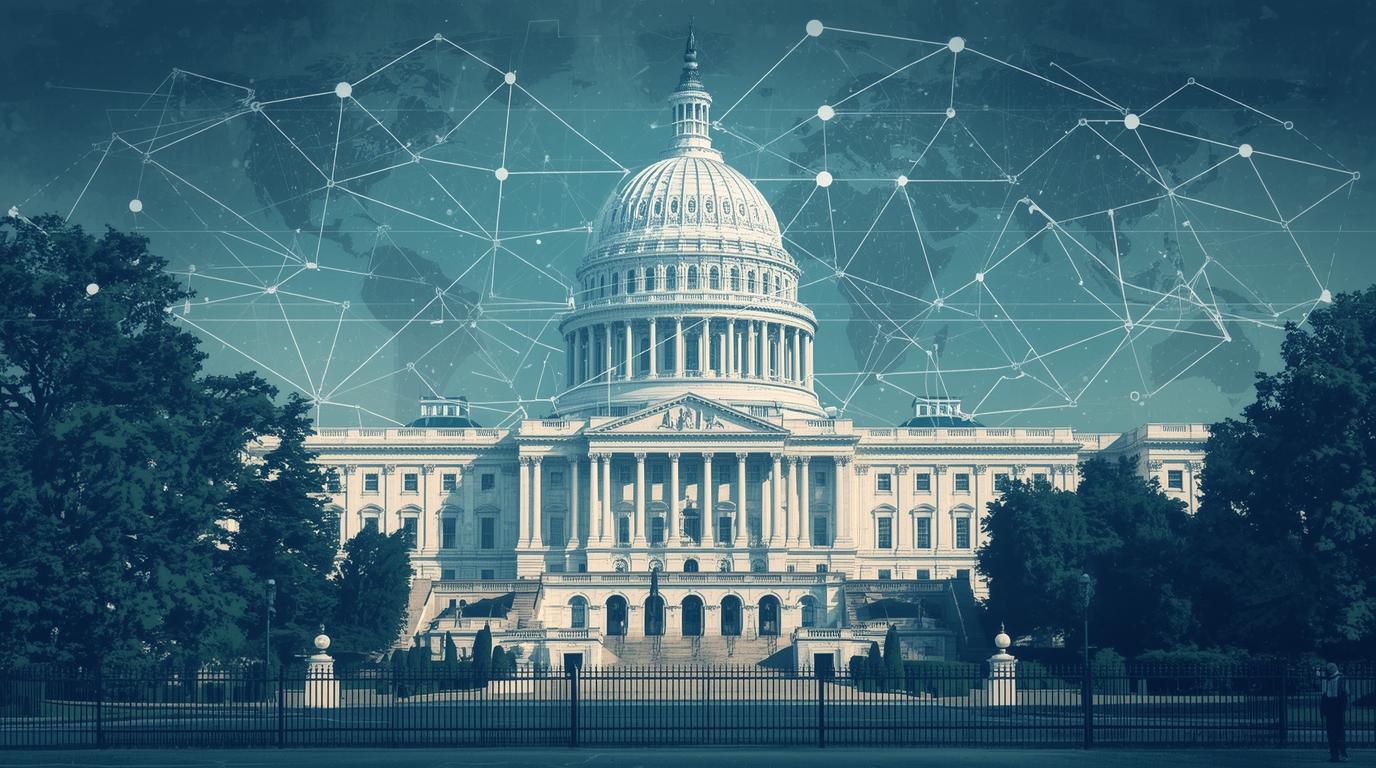三菱UFJ・みずほ・三井住友の3行が、円建てステーブルコインを共通規格で発行へ
三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の3行が、共通規格に基づく円建てステーブルコインを年内にも実用化する方針を固めた。
日本経済新聞の報道によると、フィンテック企業Progmat(プログマ)のシステムを活用し、銀行間で相互運用が可能なデジタル通貨基盤を構築する。
目次
共通規格による企業間決済の効率化
この仕組みにより、異なる銀行間でも相互に送金・決済が行えるようになり、法人取引の利便性が大幅に向上する見通しだ。
第一弾として三菱商事が社内決済での利用を検討しており、将来的には米ドル建てステーブルコインの発行も視野に入っているという。
ブロックチェーン技術による国際送金改革
3行は、法人向けの低コスト決済インフラとしてステーブルコインの普及を目指している。
ブロックチェーンを活用することで、国際送金の手数料と時間を大幅削減し、30万社超の取引先を持つメガバンク連携による国内利用拡大を狙う。
「米国主導のドル建てステーブルコインが日本市場を席巻する前に、円建てデジタル通貨の標準化を目指す」── 関係者談(報道より)
信託型スキームでリスクと保護を両立
今回のプロジェクトでは三菱UFJ信託銀行も参加し、裏付け資産を信託口座で管理する「信託型」スキームを採用する見通し。
この仕組みは2023年施行の改正資金決済法に基づく電子決済手段に該当し、発行者の資産と裏付け資産を分別管理することで投資家保護を強化できる。
- 発行者資産と信託資産を明確に分離
- 資金移動業ライセンス不要で銀行が参入可能
- 改正資金決済法の第三号電子決済手段に準拠
デジタル円構想が現実味を帯びる
今年8月にはJPYC社が金融庁に登録を完了し、国内初の円建てステーブルコインを年内に発行予定。
これに続き、三井住友銀行とSBI VCトレードがステーブルコイン流通基盤を共同開発するなど、民間主導のデジタル円構想が加速している。
国内金融システムの新たな転換点
今回の3行連携は、円建てステーブルコインを通じて既存の円預金と同等の信頼性を持つ決済手段を生み出す試みといえる。
実用化が実現すれば、国内企業間取引の効率化だけでなく、日本の金融インフラの国際競争力向上にも寄与すると期待されている。