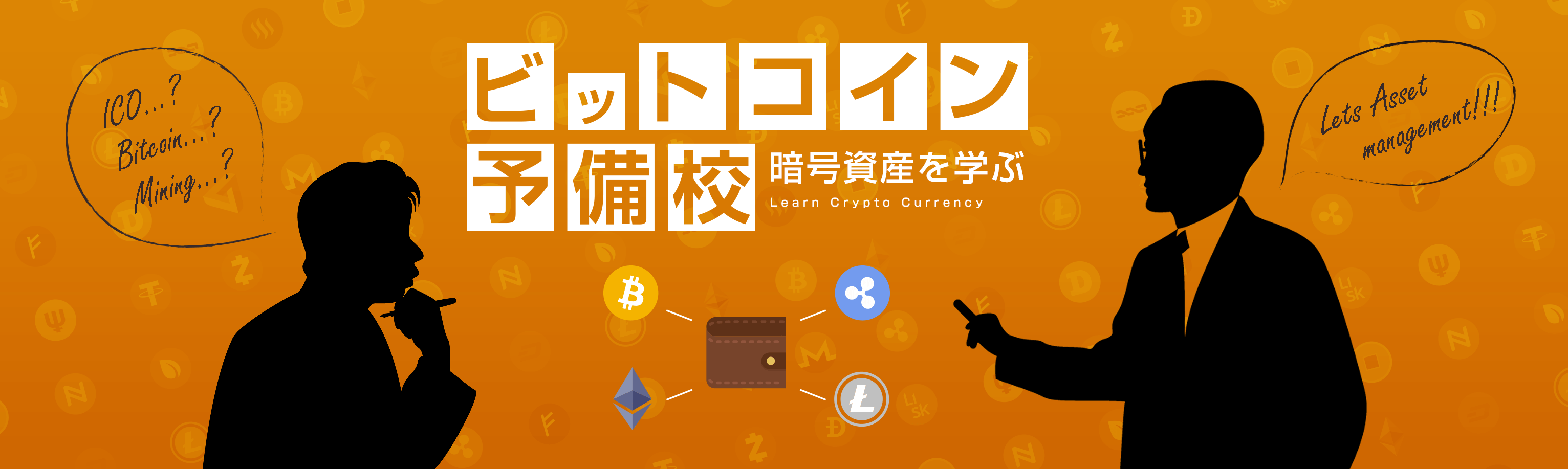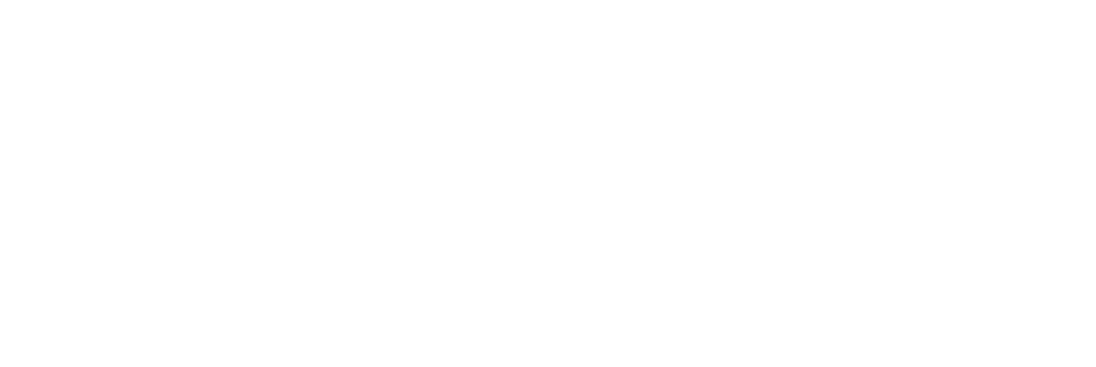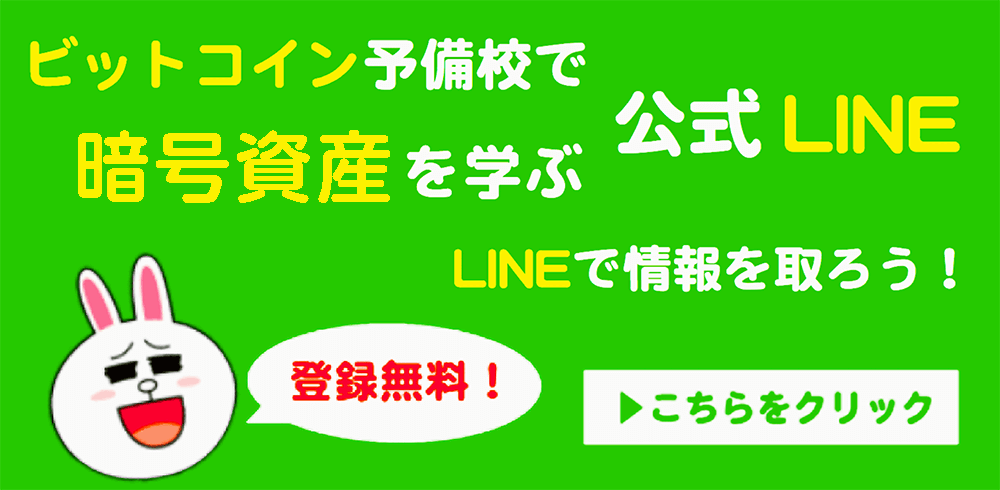2025年11月13日、米国最大級の金融機関JPモルガン・チェースが、イーサリアムのレイヤー2ブロックチェーン「Base」上で米ドル建て預金トークンの提供を開始しました。
暗号資産取引プラットフォームB2C2、コインベース、決済大手マスターカードがテストを完了し、実運用フェーズに移行しています。
目次
大手金融機関が選んだイーサリアムL2という選択
この動きは、単なる技術的な実験ではありません。
従来、JPモルガンは独自のプライベートブロックチェーン「Quorum」(後にConsenSysに売却)やJPMコインをプライベートネットワーク上で展開してきました。
しかし今回、パブリックなイーサリアムエコシステムの一部であるBaseを選択したことは、大手金融機関が「分散型インフラの実用性」を本格的に評価し始めた証拠といえるでしょう。
JPモルガンが開発したデジタル通貨で、1JPMコイン=1米ドルの価値を持つステーブルコイン型のトークンです。
従来は機関投資家向けの決済や証券取引の即時決済に使用されてきましたが、今回Baseへの展開により、より広範なDeFiエコシステムとの相互運用性が期待されます。
なぜ「Base」が選ばれたのか?
Baseは、コインベースが開発したイーサリアムのレイヤー2ソリューションで、Optimismのスタック技術を活用しています。
低コスト、高速なトランザクション処理、そしてイーサリアムメインネットとの高いセキュリティ互換性を兼ね備えています。
JPモルガンがBaseを選択した理由は、以下の3点に集約されます。
1. コスト効率とスピード
イーサリアムメインネットでは、ガス代が高騰する局面が依然として存在します。
金融機関が大量の決済を処理する際、1件あたりのコストが数ドルに達することは受け入れがたい水準です。
Baseのようなレイヤー2では、トランザクションコストを数セントレベルに抑えながら、決済の即時性を確保できます。
2. コインベースとの戦略的提携
コインベースは米国最大の暗号資産取引所であり、機関投資家向けのカストディサービスでも高い信頼性を誇ります。
JPモルガンがBaseを選択した背景には、コインベースとの既存の取引関係や、今後のDeFi分野での協業を視野に入れた戦略的判断があると考えられます。
3. パブリックチェーンへの段階的移行
従来のプライベートブロックチェーンは、参加者が限定されるため流動性や相互運用性に課題がありました。
一方、完全にパブリックなイーサリアムメインネットは、規制やコンプライアンスの観点からハードルが高い。
Baseは、その中間に位置する「準パブリック」な環境として、金融機関にとって現実的な選択肢となっています。
今回の動きは、ビットコインのような「完全分散型」ネットワークとは異なる路線ですが、金融機関がブロックチェーン技術を「実用ツール」として認識し始めた転換点と捉えることができます。
ビットコインが「価値保存」の役割を担う一方、イーサリアムエコシステムは「金融インフラの再構築」という別の役割を果たしつつあります。
テスト完了企業の顔ぶれが示す未来
今回、JPMコインのBase上でのテストに参加したのは、B2C2、コインベース、マスターカードという3社です。
それぞれの企業が持つ専門性が、今後の展開の方向性を示唆しています。
B2C2(機関投資家向け流動性プロバイダー)
B2C2は機関投資家向けの暗号資産流動性プロバイダーであり、大口取引における即時決済のニーズが高い企業です。
JPMコインがBase上で機能することで、暗号資産と法定通貨の橋渡しがよりスムーズになり、機関投資家の参入障壁がさらに低下します。
コインベース(カストディ最大手)
コインベースは、Base自体の開発者であり、暗号資産カストディの最大手でもあります。
同社がJPモルガンと協業することで、機関投資家向けサービスの信頼性が一層向上します。
また、コインベースは最近、トークンセールプラットフォームの立ち上げも発表しており、今後JPMコインを活用した新たな資金調達手段が登場する可能性もあります。
マスターカード(グローバル決済網)
マスターカードは、伝統的な決済ネットワークの巨人です。
同社がJPMコインのテストに参加した意味は大きく、将来的にはマスターカードのグローバル決済網とブロックチェーンベースのトークンが統合される未来が見えてきます。
たとえば、クレジットカード決済の裏側でJPMコインが動作し、リアルタイムでの国際送金が実現する——そんなシナリオも現実味を帯びてきました。
JPMコインのBase展開は、「ブロックチェーンは投機的なものではなく、実用的な金融インフラである」という認識を広める重要な一歩です。
特に、規制が厳しい米国において大手金融機関がパブリックチェーン技術を採用したことは、今後の業界全体の方向性を示す重要なシグナルといえます。
今後の展望と課題
JPMコインのBase展開は始まったばかりですが、いくつかの課題も残されています。
規制とコンプライアンスの整備
Baseはパブリックチェーンの一種であり、誰でもトランザクションを閲覧できます。
金融機関が扱う顧客情報やトランザクションの機密性をどのように確保するかは、今後の大きな課題です。
ゼロ知識証明などのプライバシー技術が導入される可能性もあります。
他のレイヤー2やブロックチェーンとの競争
Arbitrum、Polygon、Optimismなど、イーサリアムのレイヤー2ソリューションは多数存在します。
JPモルガンがBaseを選んだ理由は明確ですが、他の金融機関が異なる選択をする可能性もあり、今後のインターオペラビリティ(相互運用性)が重要になります。
ステーブルコインとの競合
USDCやUSDTといった既存のステーブルコインは、すでに広範なエコシステムを構築しています。
JPMコインがこれらと差別化を図るためには、機関投資家向けの信頼性や、既存の金融システムとのシームレスな統合が鍵となるでしょう。
JPMコインはあくまで「中央集権的なステーブルコイン」であり、JPモルガンが発行・管理を行います。
これは、ビットコインのような「検閲耐性」や「非中央集権性」とは異なる性質です。
金融機関が主導するブロックチェーンプロジェクトには、常に中央集権化のリスクが伴うことを理解しておく必要があります。
結論——金融インフラの静かな革命
JPモルガンのJPMコインがBase上で展開を開始したことは、暗号資産業界における「静かな革命」の一部です。
派手な価格高騰や投機的なニュースとは異なり、地道に金融インフラを再構築する動きこそが、長期的には最も重要な変化をもたらします。
ビットコイン予備校の視点から見れば、この動きは「ビットコインの分散型哲学」と「伝統的金融システムの効率性」が融合する過程の一つです。
両者は対立するものではなく、それぞれ異なる役割を果たしながら、新しい金融エコシステムを形成していくでしょう。
今後、JPMコインのようなトークンがどのように普及し、私たちの日常の決済や投資活動にどのような影響を与えるのか。
その動向を注視していくことが、暗号資産の未来を理解する上で不可欠です。