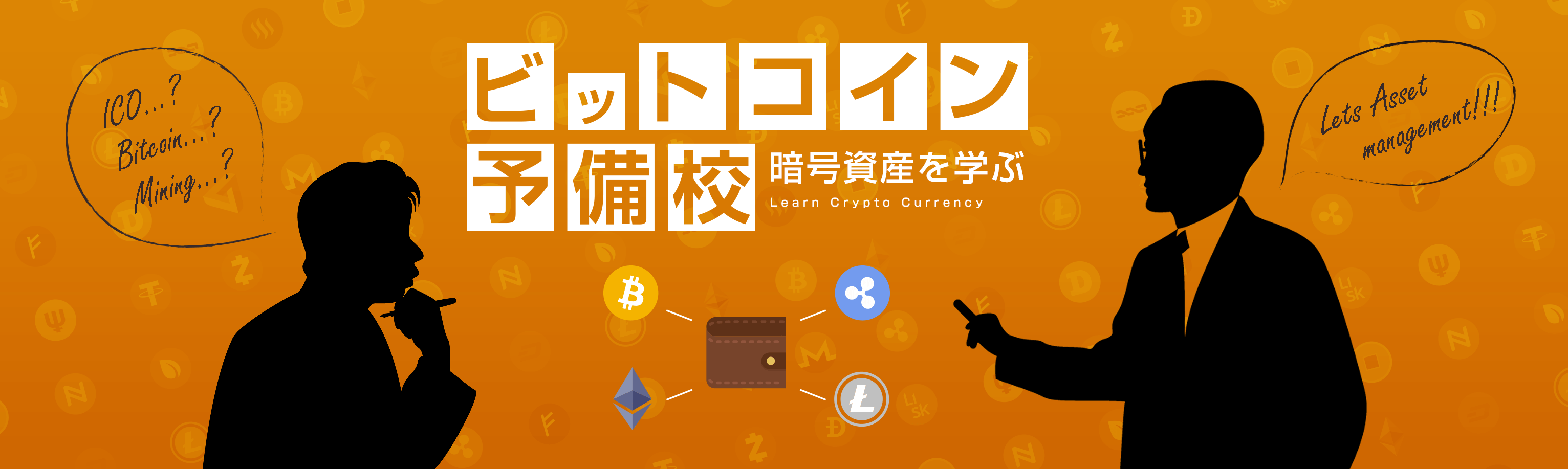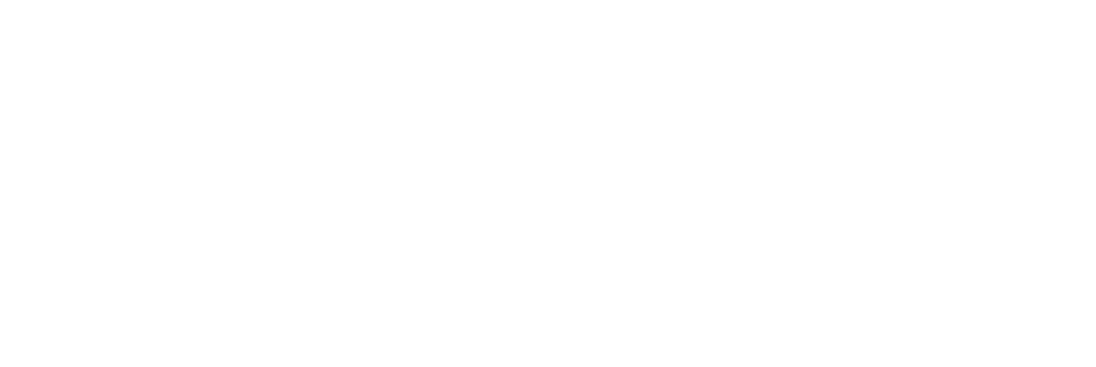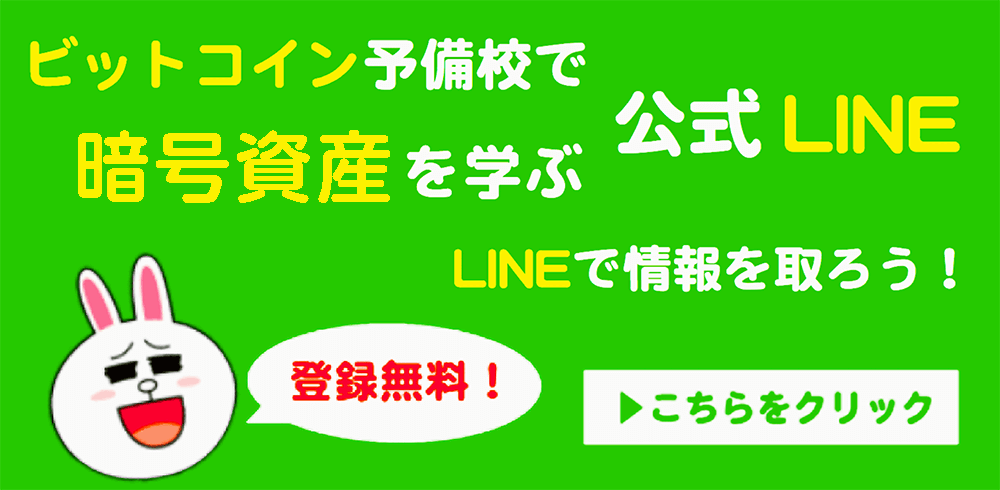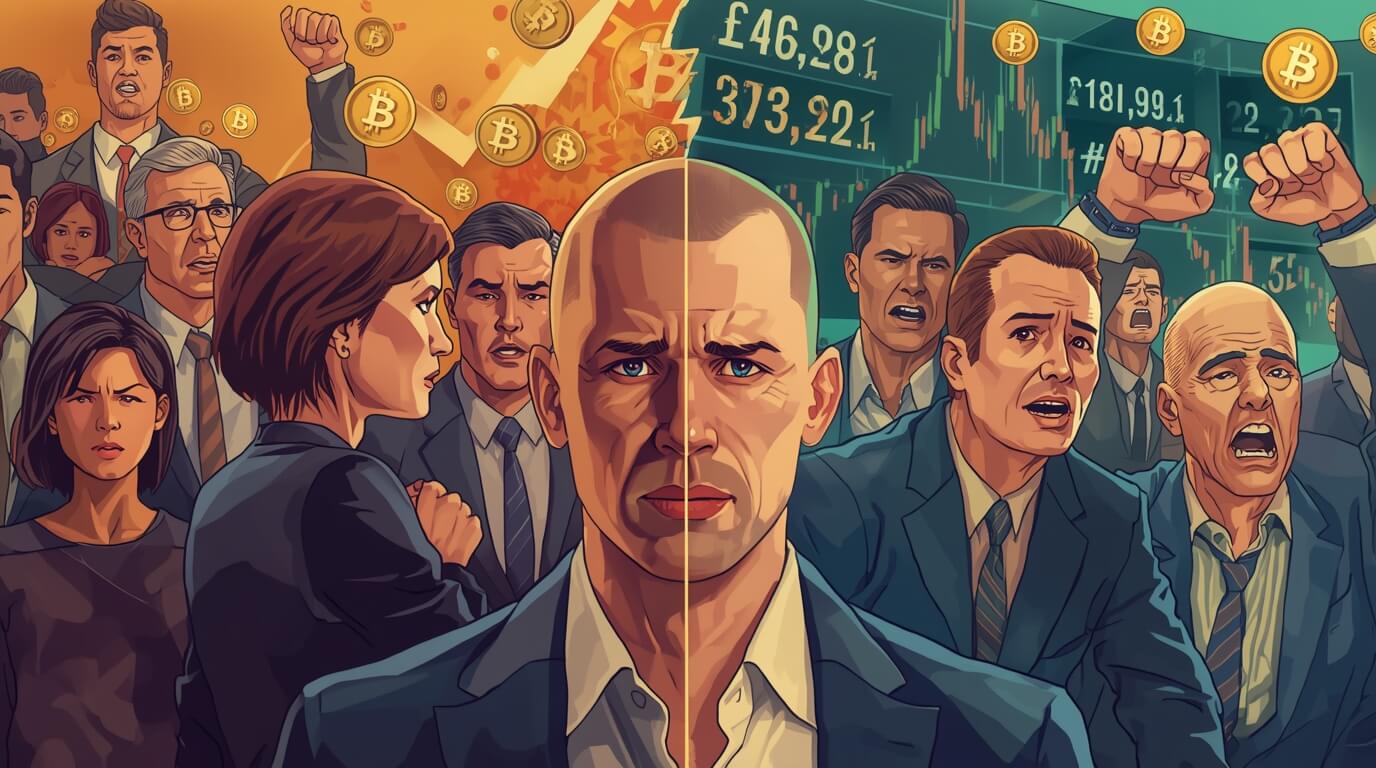2025年11月13日、米国証券取引委員会(SEC)の委員長が、仮想通貨のトークン分類体系を「数カ月以内」に明確化する方針を表明しました。
この発表は、長年にわたって業界を悩ませてきた「どのトークンが証券に該当するのか?」という根本的な疑問に、ついに明確な答えが示される可能性を示唆しています。
目次
長年の不透明さに終止符を打つ動き
米国では、トークンが証券に該当するかどうかを判断する基準として「ハウイテスト(Howey Test)」が用いられてきました。
これは、1946年の最高裁判例に基づく古典的な基準ですが、暗号資産のような新しい技術に対してどのように適用されるべきかは、長らく曖昧なままでした。
その結果、多くのプロジェクトがSECから訴訟を受け、業界全体に不確実性が広がっていました。
ハウイテストは、ある取引が「投資契約」に該当するかを判断する4つの基準です。
- ①金銭の投資
- ②共同事業
- ③利益の期待
- ④他者の努力による利益
この4つを満たす場合、証券として規制対象となります。
しかし、暗号資産の世界では、この基準の適用が非常に複雑で、プロジェクトごとに判断が分かれてきました。
「ネットワークトークン」と「ミームコイン」は管轄外見込み
今回の発表で特に注目されるのは、SEC委員長が「ネットワークトークン」や「ミームコイン」は管轄外になる見込みであることを示唆した点です。
これは、業界にとって大きな前進といえます。
ネットワークトークンとは?
ネットワークトークンとは、ブロックチェーンのネットワークを維持・運営するために必要なトークンを指します。
たとえば、イーサリアムのETHや、ソラナのSOLなどが該当します。
これらは、ネットワークのガス代(手数料)として使用されたり、ステーキングによってネットワークのセキュリティを支えたりする役割を果たしています。
従来、SECはこれらのトークンについても「発行時の資金調達方法によっては証券に該当する」という立場を取ってきました。
しかし、ネットワークが十分に分散化され、発行者による中央集権的なコントロールがなくなった場合、証券性は薄れるという解釈も存在します。
今回の明確化により、こうしたトークンが証券規制から外れる可能性が高まりました。
ミームコインについて
ミームコインについても同様です。
ドージコインやシバイヌのようなミームコインは、特定の企業や開発チームが利益を追求するために発行されたものではなく、コミュニティ主導で価値が形成されています。
ハウイテストの「他者の努力による利益」という要件を満たさないため、証券には該当しないという解釈が妥当です。
ネットワークトークンとミームコインがSECの管轄外となることで、これらのトークンを扱う取引所やプロジェクトは、証券規制を気にせずに活動できるようになります。
これにより、イノベーションが加速し、より多くのプロジェクトが米国市場で展開しやすくなるでしょう。
どのトークンが「証券」に該当するのか?
では、逆にどのようなトークンが証券に該当する可能性が高いのでしょうか?
今回の明確化で焦点となるのは、以下のような特徴を持つトークンです。
1. ICOや資金調達目的で発行されたトークン
2017年から2018年にかけてのICOブーム期には、多くのプロジェクトが「将来の利益」を約束してトークンを販売しました。
こうしたトークンは、ハウイテストの「投資契約」に該当する可能性が高く、SECの規制対象となります。
2. 配当や利益分配を約束するトークン
トークン保有者に対して、プロジェクトの収益を配当として分配する仕組みを持つトークンは、明確に証券の性質を持ちます。
たとえば、プロトコルの手数料収益をトークンホルダーに分配するようなモデルは、証券規制の対象となる可能性が高いでしょう。
3. 中央集権的な管理体制を持つトークン
特定の企業や開発チームがトークンの発行量や価格をコントロールできる場合、そのトークンは証券とみなされる可能性があります。
逆に、完全に分散化されたネットワークで、誰もコントロールできない状態になっていれば、証券性は低下します。
ビットコインが証券ではないとされる理由は、まさにこの「分散化」にあります。
ビットコインは創設者のサトシ・ナカモトが姿を消し、誰も中央集権的なコントロールを持たないため、ハウイテストの要件を満たしません。
今回のSECの明確化は、ビットコインのような完全分散型のモデルが、規制の観点からも理想的であることを再確認するものといえます。
明確化がもたらす業界への影響
SECによるトークン分類体系の明確化は、暗号資産業界に以下のような影響をもたらすと考えられます。
1. プロジェクトの透明性向上
これまで、多くのプロジェクトは「SECに訴えられるかもしれない」という不安を抱えながら活動してきました。
明確な基準が示されることで、プロジェクトは自らのトークンが証券に該当するかどうかを事前に判断し、適切なコンプライアンス体制を構築できるようになります。
2. 取引所のリスク軽減
米国の暗号資産取引所は、未登録の証券を取り扱ったとしてSECから訴訟を受けるリスクを常に抱えています。
実際、コインベースやバイナンスUSもSECから訴訟を受けた経緯があります。
明確な分類基準が示されることで、取引所は安心してトークンの上場判断を行えるようになります。
3. 投資家保護の強化
証券に該当するトークンについては、適切な情報開示や投資家保護の仕組みが求められます。
これにより、詐欺的なプロジェクトが淘汰され、健全な市場環境が形成されるでしょう。
4. 国際的な規制調和の促進
米国がトークン分類の明確な基準を示すことで、他国も追随する可能性があります。
欧州のMiCA規制や、日本の金融庁による規制との整合性が取れるようになれば、グローバルな暗号資産市場の成長が加速します。
規制の透明性が向上することで、企業や開発者は安心して新しいプロジェクトに挑戦できるようになります。
これは、暗号資産業界全体のイノベーションを加速させる重要な要因となるでしょう。
残された課題と今後の展望
SECによる明確化は大きな前進ですが、いくつかの課題も残されています。
既存のトークンに対する取り扱い
過去にICOで発行されたトークンの中には、現在は十分に分散化が進んでいるものもあります。
これらのトークンが「過去は証券だったが、現在は証券ではない」という判断を受けるのか、それとも「一度証券になったものは永遠に証券」とみなされるのか、明確な指針が必要です。
DeFiプロトコルのガバナンストークン
UniswapのUNIやAaveのAAVEのようなトークンは、プロトコルの運営方針を決定する投票権を持ちますが、直接的な利益分配はありません。
こうしたトークンが証券に該当するかどうかは、依然として議論の余地があります。
NFTやゲームアイテムの扱い
一部のNFTは、将来的な価値上昇を期待して購入されるため、投資契約の性質を帯びる可能性があります。
ゲーム内アイテムも、リアルマネーで取引される場合は証券性が問われるかもしれません。
明確化は歓迎すべきことですが、過度に厳格な基準が設けられると、イノベーションが阻害される恐れもあります。
SECは、投資家保護と業界の成長のバランスを慎重に取る必要があります。
結論——透明性がもたらす業界の成熟
米SEC委員長による仮想通貨分類体系の明確化は、暗号資産業界が「成熟期」に入るための重要なステップです。
長年の不透明さに終止符が打たれることで、企業、投資家、規制当局の三者が共通の理解を持ち、健全な市場環境を構築できるようになります。
ビットコイン予備校の視点から見れば、この動きは「規制と自由のバランス」を模索する過程の一部です。
ビットコインが目指した「検閲耐性」や「非中央集権性」という理念は、規制が厳しくなる中でますます重要性を増しています。
一方で、適切な規制が投資家を保護し、業界全体の信頼性を高めることも事実です。
今後数カ月以内に発表される具体的な分類基準に注目しながら、業界がどのように変化していくのかを見守りましょう。
透明性の向上が、暗号資産の未来をより明るいものにすることを期待しています。