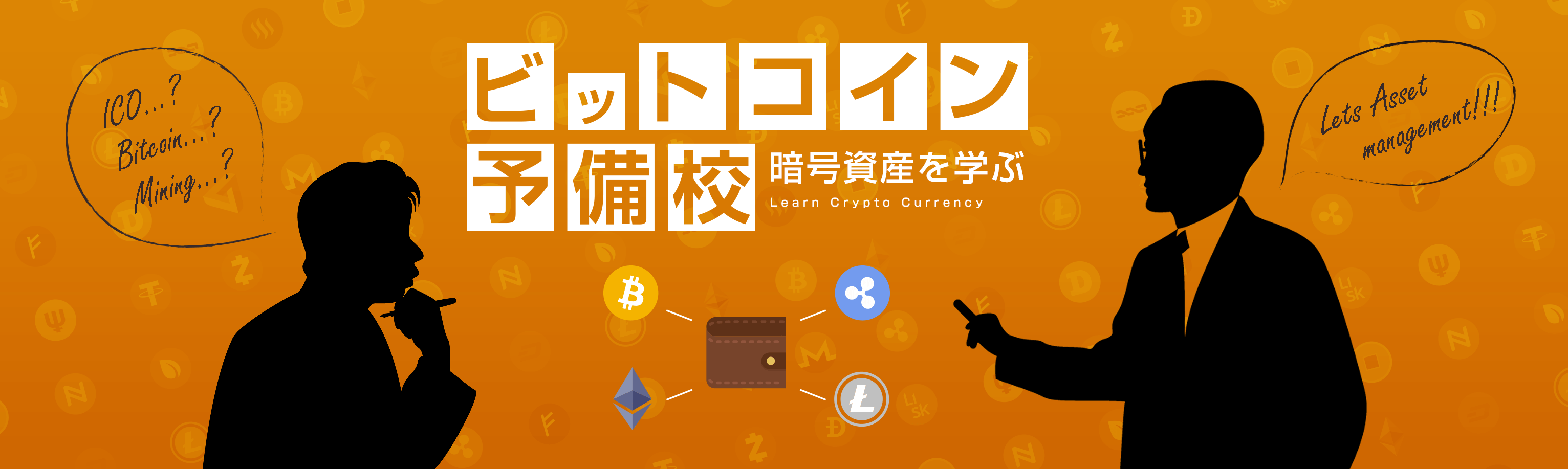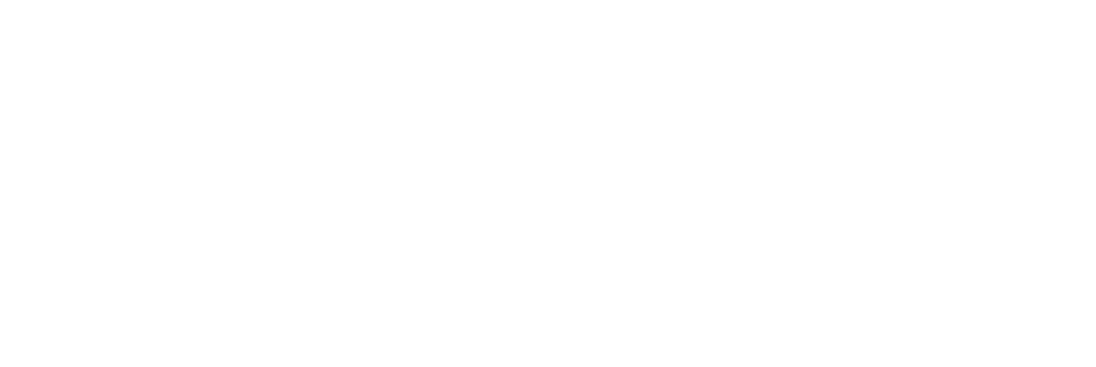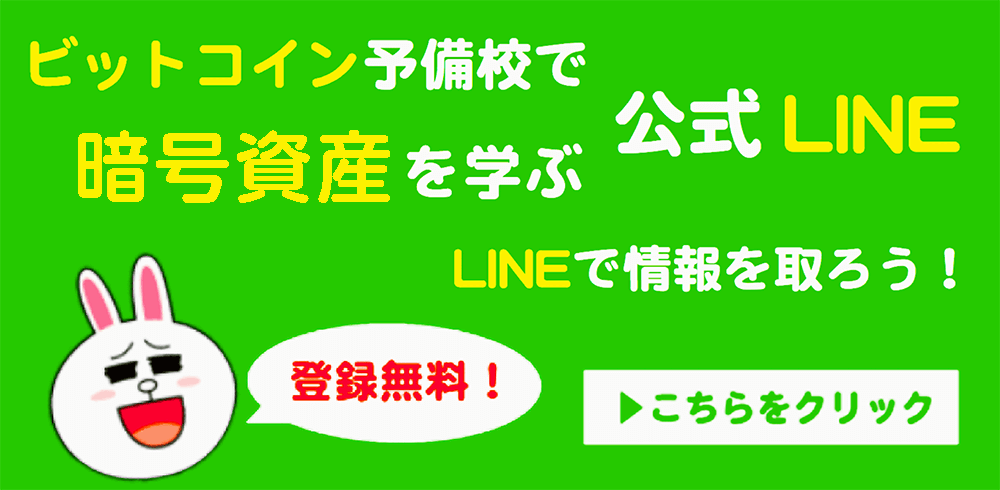目次
2025年11月12日──予想を覆す「連続流入記録」
2025年10月28日、ビットワイズのBSOL、29日にグレースケールのGSOLが米国市場に上場したソラナ(SOL)現物ETFが、取引開始から10日間連続で資金純流入を記録した。SoSoValueのデータによれば、11月10日時点で2商品の純資産総額は約6億ドル(約922億円)に達し、ソラナの時価総額の0.64%に相当する。
この記録について、LVRGリサーチのディレクター、ニック・ラック氏は「上場前の期待を大きく上回っている」と評価した。もともと規制と技術のリスクが指摘され、機関投資家による投資はもっと少ないと予測されていたのだ。
①10日間連続の資金純流入:上場初日から一度も流出せず、事前予想を大きく上回る
②純資産総額6億ドル:ソラナ時価総額の0.64%を占め、初期段階としては好調
③ビットコイン・イーサリアムETFとの対比:同期間、BTC/ETH ETFは2日間しか流入がなかった
イーサリアムETFの「失敗」と比較して見えるもの
ソラナETFの成功を際立たせるのは、イーサリアムETFの低調な滑り出しとの対比である。2024年7月に承認されたイーサリアム現物ETFは、承認直後こそ話題を集めたものの、資金流入は期待外れに終わった。グレースケールのGBTC(グレースケール・ビットコイン・トラスト)からの大規模な資金流出が影響し、ネット流入は限定的だった。
さらに、イーサリアムETFにはステーキング報酬が含まれないという制約があった。イーサリアムを直接保有すれば年率3〜5%のステーキング報酬が得られるが、ETFではそれが得られない。この競争劣位が、機関投資家の参入を躊躇させた一因とされている。
対してソラナETFは、上場初日から連続流入を記録している。10月28日から11月10日までのデータでは、ビットコインとイーサリアムのETFが純流入したのはわずか2日間だった。ソラナETFの10日間連続流入は、明らかに異質な現象である。
「ハイベータ」戦略──機関投資家の新たな選択
ラック氏は、投資家がソラナETFを「ビットコインやイーサリアムのETFを補完する商品」とみていると指摘した。ソラナのETFは「high-beta(ハイベータ)」、つまり相場全体よりも価値が大きく変動する商品と認識されている。
ベータ値とは、市場全体の動きに対する個別資産の感応度を示す指標だ。ビットコインのベータ値を1とすれば、ソラナは1.5〜2程度とされる。市場が10%上昇すれば、ソラナは15〜20%上昇する可能性がある──逆もまた然りだが、機関投資家はこの「高いリスク調整後リターン」を狙っているのである。
「投資家はアルトコインが上昇する相場において潜在的なリスク調整後リターンを狙うために、大きな価格変動を受け入れている」──ラック氏のこの分析は、機関投資家の戦略変化を示唆している。2024年のビットコイン現物ETF承認以降、暗号資産市場は「ビットコイン一強」から「アルトコインへの分散」へと移行しつつある。ソラナETFへの連続流入は、その象徴的な現象なのだ。
供給抑制と機関マネーの好循環
ラック氏は、現物ETFへの持続的な資金流入がソラナの供給を抑制し、価格の好材料になると指摘した。ETFがソラナを買い入れると、その分だけ市場の流通量が減少する。需要が一定であれば、供給減少は価格上昇圧力となる。
さらに、ETFの存在自体が機関投資家の資金が流入しやすい環境を構築する。従来、機関投資家がソラナを保有するには、カストディアン(資産保管業者)の選定、ウォレットのセキュリティ対策、規制上のコンプライアンス対応など、複雑な手続きが必要だった。
しかし、ETFを通じれば、既存の証券口座で購入でき、税務処理も簡便である。この「参入障壁の低下」が、機関マネーの流入を加速させている。ソラナETFの6億ドルという純資産総額は、初期段階としては極めて健全な数字だ。イーサリアムETF上場初週の流入額と比較しても遜色ない。
技術的優位性が評価される時代へ
ソラナETFへの連続流入は、単なる投機ではなく、ソラナの技術的優位性が機関投資家に評価されている証拠でもある。ソラナは、秒間数万トランザクションを処理できる高速性と、1セント以下の取引手数料を実現している。
イーサリアムがレイヤー2ソリューション(Arbitrum、Optimismなど)に依存してスケーラビリティを確保しているのに対し、ソラナはレイヤー1単体で高速処理を実現している。この技術的シンプルさが、開発者とユーザーの双方に支持されている。
2024年以降、ソラナ上ではMeme Coins(ミームコイン)ブームが起こり、Pump.funなどのプラットフォームが爆発的に成長した。また、DeFi(分散型金融)やNFT市場でもソラナのシェアが拡大している。こうした「実需」の増加が、機関投資家の評価につながっているのだ。
ラック氏は「ソラナの時価総額はビットコインの5%、イーサリアムの22%だ」と述べた。これは、ソラナがまだ成長余地を大きく残していることを意味する。イーサリアムおよびビットコインETFで見られた資金流入を相対的に維持した場合、最初の12〜18ヶ月で30億ドル規模の流入も視野に入る。ソラナETFの純資産総額が現在の6億ドルから5倍に成長すれば、ソラナの時価総額シェアはさらに拡大する。
イーサリアムの「逆襲」はあるか?
ソラナETFの好調は、イーサリアムETFの停滞を際立たせている。しかし、2025年11月11日、米財務省が仮想通貨ETFのステーキング報酬分配を正式承認した。これにより、イーサリアムETFもステーキング報酬を投資家に分配できるようになる。
この規制変更は、イーサリアムETFの競争力を大幅に向上させる。年率3〜5%のステーキング報酬が加われば、イーサリアムETFは「価格上昇+インカムゲイン」の二重の魅力を持つ商品となる。2026年以降、イーサリアムETFが反撃に転じる可能性は十分にある。
しかし、現時点ではソラナETFが明確な優位を築いている。10日間連続流入という記録は、機関投資家の選択がソラナに傾いていることを示す明確なシグナルだ。
【ビットコイン予備校の視点】機関マネーの「質」を見極める
このニュースから初心者が学ぶべきは、「資金流入の継続性」の重要性である。暗号資産市場では、一時的な資金流入(ポンプ)が頻繁に起こる。しかし、それが持続しなければ、価格は元に戻る。
ソラナETFの10日間連続流入は、「一過性のブーム」ではなく「構造的な需要」を示している。機関投資家は短期的な投機ではなく、長期的なポートフォリオ戦略としてソラナETFを組み入れているのだ。
初心者投資家が注目すべきは、短期的な価格変動ではなく、こうした「資金の流れの質」である。ソラナがイーサリアムを技術的に上回っているかどうかは議論の余地があるが、少なくとも現時点で機関投資家は「ソラナの方がリスク調整後リターンが高い」と判断している。
この「機関マネーの選択」を理解することが、賢明な投資判断の基礎となる。ソラナETFの連続流入は、単なる数字ではなく、暗号資産市場における「価値評価の変化」を映し出す鏡なのである。
参照元
- ソラナ現物ETF、取引開始から10日間連続で資金が純流入 – CoinPost
- Spot Solana ETFs see tenth consecutive day of inflows – The Block
- US Solana Spot ETF Data – SoSoValue