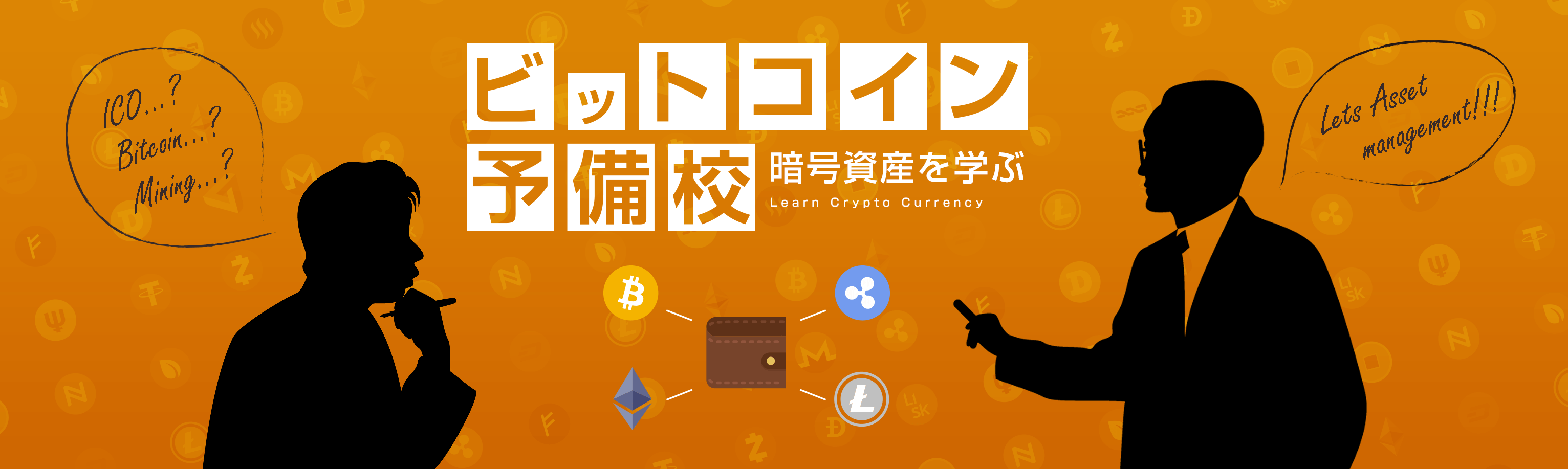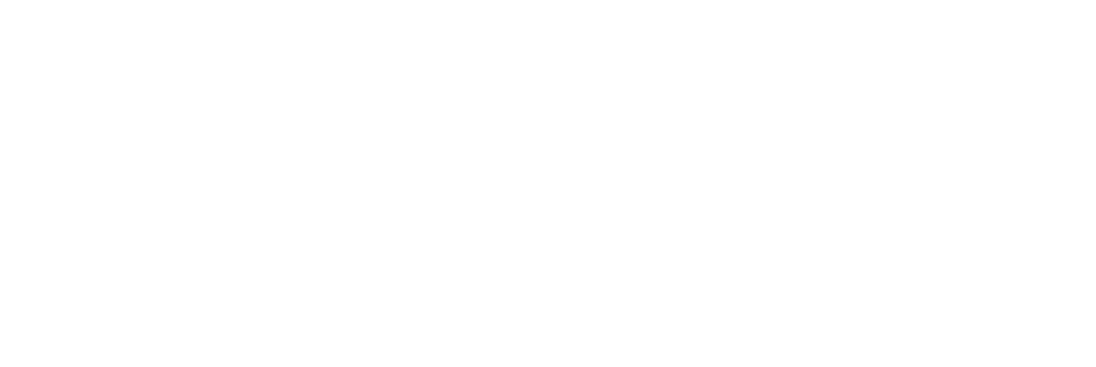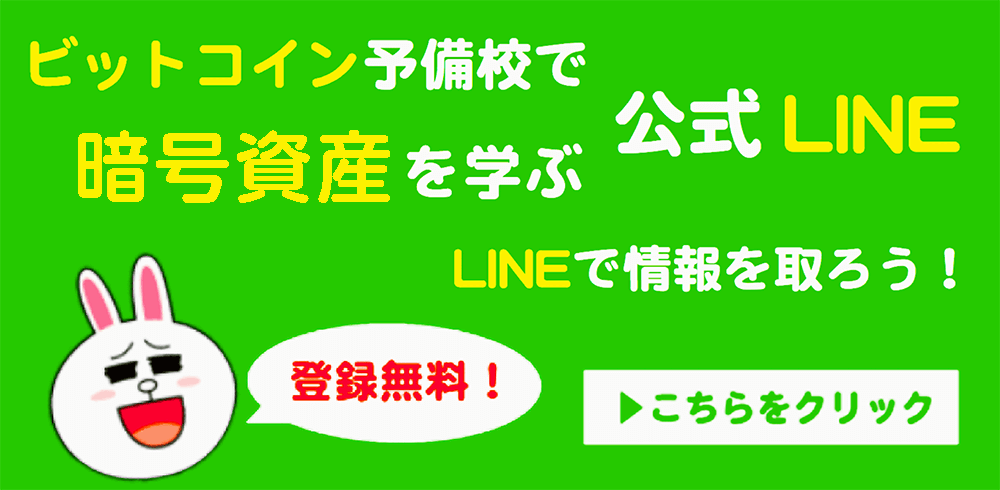未公開情報を利用した取引に課徴金、金商法改正案を2026年に提出予定
金融庁が仮想通貨(暗号資産)のインサイダー取引を禁じる新たな法規制を導入する方針を固めた。
15日付の日本経済新聞の報道によると、未公開情報をもとにした売買を禁止し、違反者に課徴金を科す規定を金融商品取引法(通称:金商法)に明記する方針だ。
目次
2026年通常国会で金商法改正へ
金融庁は年末までに作業部会で詳細を詰め、2026年の通常国会で改正案を提出する見込み。
また、証券取引等監視委員会(SESC)が犯則調査の対象とし、疑わしい取引が確認された場合には課徴金勧告や刑事告発まで踏み込むことが可能となる。
「公平な市場形成と投資家保護の強化が狙い。仮想通貨を実質的な金融商品として位置づける転換点になる」
── 金融庁関係者(報道より)
自主規制から法的監視体制へ
これまで日本では、仮想通貨取引に関しては交換業者や日本暗号資産取引業協会(JVCEA)による自主規制が中心だった。
しかし、近年の市場拡大により、取引データ監視や情報開示体制の限界が指摘されていた。
金融庁による監視体制が整うことで、市場の信頼性と透明性が向上することが期待されている。
- 未公開情報の例:上場計画、ハッキング・セキュリティリスク、提携発表前情報など
- 課題:仮想通貨は明確な発行主体が存在しないケースが多く、情報源の特定が困難
- 今後、適用範囲の明確化と実務上の定義づけが焦点に
過去の海外事例と国内影響
海外では、コインベースの元社員が上場前情報を悪用して約1.38億円の不正利益を得た事件や、
バイナンス社員によるインサイダー取引疑惑などが確認されている。
これを受けて、日本でも仮想通貨を「金融商品」として法的整備を進める</strong動きが本格化している。
今後の見通し
金融庁は、仮想通貨を決済手段というよりも投資対象として位置づける方向</strongを明確にしている。
法的な枠組み整備により、公正で透明な市場形成が期待される一方、情報定義の難しさや国際的な整合性確保が今後の課題となる。